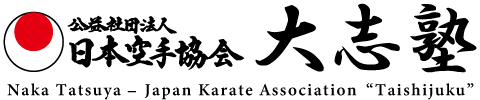大志塾だより / Taishijuku letters
「大志塾だより」 49号
2009年2月3日
心は常に大を志向せよ! 「以武会友」武道を以て友となす 我々が追究する武道空手の本質とは 「道」・究極の術技をもとめて 第4回 型に於いて頻度の高い個々の技を抜き出し、技を徹底して深く掘り下げて、技の原理原則を学 […]
「大志塾だより」 48号
2009年1月29日
心は常に大を志向せよ! 「以武会友」武道を以て友となす ?H3>志水亮介先生 2度目のV 去る7月8日(日)日本武道館に於いて開催された「内閣総理大臣杯 第51回全国空手道選手権大会」で、志水先生が個人組手の部に於い […]
「大志塾だより」 47号
2009年1月29日
心は常に大を志向せよ! 「以武会友」武道を以て友となす 「道」・究極の術技を求めて 第2回 前号で書きましたが(読み直してください)西洋的近代スポーツ思想に立脚した競技空手では、ポイント重視による「数」「結果」に価 […]
「大志塾だより」第46号が出来ました。
2008年1月24日
心は常に大を志向せよ! 「以武会友」武道を以て友となす 皆様、新年明けましておめでとうござ います。 本年も武道空手の真髄に一歩でも近づける様、大志塾塾生一丸となって、努力・ 精進して行きましょう。我々が追究する 武道 […]